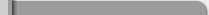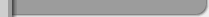大倉陶園テーブルウェア通信販売のご案内
|
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
金彩の上に凛と咲く椿を墨絵のような上絵で描いた、日本人の美意識を刺激する高貴なイメージの器です。
金の縁飾りには、今や大倉陶園のみが有する貴重な技法「エンボス」を用いており、ディナー用、ティー用としての用途の他、インテリアとしてもお使い頂けます。 ※エンボスとは 金色の模様を浮き出させるエンボス技法。型抜き直後の柔らかい成形生地にローラーを回転させながら模様を刻み込み、その部分のみ釉を施さず本焼きし、その後さらに金を焼き付けるという大変に繊細で複雑な装飾技法です。高度の熟練を要するため、今日では大倉陶園だけが保持する貴重な技能遺産となっております。 |
||
 |
||
2019年に大倉陶園創業100周年を迎えるにあたり、「良きが上にも良きものを」をコンセプトに江戸切子との初コラボレーションで発表された記念作品です。
コバルト絵具の群青が釉薬とやわらかに融合した炎の芸術から生まれた人気のブルーローズが、カガミクリスタル社製江戸切子と共に優雅なランプスタンドになりました。 炎の芸術が創り出す神秘の色彩「ブルーローズ」。1928年の発表以来多くの方々に愛されて続けている、大倉陶園を代表するデザインです。ブルーローズの愛称で親しまれる青いバラは大倉陶園独自の技法「岡染」により完成されます。「岡染」は1460度で焼成した生地に油で溶いたコバルト質顔料で絵を描き、再び1460度で本焼成します。すると顔料は釉に沈み深く青く優しい大倉陶園独特のブルーローズが完成します。大倉陶園の白い生地に自然には存在しないブルーローズが群青のバラを咲かせます。 江戸切子は、天保5年(1834年)に、江戸の大伝馬町でビードロ屋を営んでいた加賀屋久兵衛という人物が、英国製のカットグラスを真似てガラスの表面に彫刻を施したのが始まりと言われています。 幕末に黒船で来航したペリー提督が、加賀屋から献上されたガラス瓶の見事な切子に驚嘆したという逸話が伝えられています。 明治時代には、英国人による技術指導によって、西洋式のカットや彫刻技法が導入されました。現代に至る精巧なカットの技法の多くはこの時に始まったとされています。江戸時代には、透明なガラスに切子が施されていましたが、現在では、「色被せ(いろきせ)」ガラスを使った製品が主流となっています。 |
||
 |
||
|
忍者ブログ [PR] |